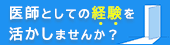神津 仁 院長
1999年 世田谷区医師会副会長就任
2000年 世田谷区医師会内科医会会長就任
2003年 日本臨床内科医会理事就任
2004年 日本医師会代議員就任
2006年 NPO法人全国在宅医療推進協会理事長就任
2009年 昭和大学客員教授就任
1950年 長野県生まれ、幼少より世田谷区在住。
1977年 日本大学医学部卒(学生時代はヨット部主将、
運動部主将会議議長、学生会会長)
第一内科入局後、1980年神経学教室へ。
医局長・病棟医長・教育医長を長年勤める。
1988年 米国留学(ハーネマン大学:フェロー、ルイジアナ州立大学:インストラクター)
1991年 特定医療法人 佐々木病院内科部長就任。
1993年 神津内科クリニック開業。
「Spasmodic dysphonia(痙攣性発声障害)」
民主党の世田谷区議会議員、Sさんからある方を紹介された。その方が患っている病気が「Spasmodic dysphonia (痙攣性発声障害) 」だった。Tさんという楚々とした物静かな女性が話すのには、この病気があまり知られていないので、患者さんはどこの病院に行って良いか分からず、何軒も医療機関を回って、時には気のせいだといわれて精神神経科で抗うつ薬や安定剤を投与されてしまう人もいる、とのことだった。この病気は、声帯を動かす筋肉が自分でコントロールすることが出来ず、不随意に痙攣して、声帯が内転(adductor type)、反対に外転(abductor type)、ふるえ(tremor type)たり、そのパターンを併せ持つ(mixed type)ものだったりして、声が出にくくなる病気だ。直接そうした患者さんを診る機会はなかなかなくて、医師にしてもこの疾患に対する知識は少ないのが実情である。
実は、大学病院に勤務していた時に私は、神経内科医として錐体外路系疾患を研究対象としていた。パーキンソン病は代表的な疾患だが、dystoniaも同時に重要な疾患の一つだ。ハンチントン舞踏病の一家系を診ていたこともあって、その脳内病態に大変興味を抱いていた頃だった。たしか、東大医学部の金澤一郎先生がハンチントン舞踏病の遺伝子を明らかにしたということで大変な注目を浴びていたと思う。
研究者の経歴や人生についていろいろと聞くと、必ず何らかの切掛けというのがあるようだ。私の場合も、ある患者さんに出会ったことで、神経内科医としての興味が錐体外路系疾患に向かったといえる。Oさんがその切掛けとなった人で、今でもその声も動きも頭の中に刻み込まれている。
Oさんは、当時50才、土建業を営んでいた。その頃私は30代の若手医師だったから、随分と年上のような感じがしたが、今自分が当時のOさんの年代を遥かに超えていることを思うと不思議な気がする。
Oさんの訴えはこうだった。「最初は、友人から右眼裂が狭くなっていると指摘されたが、そのままにしていた。自分でも、目が閉じてしまって困るので、右手の指で瞼をこじ開けるようにしていて、それが人から見ると異様に見えたようだった」 これが昭和52年1月末のことだ。
その後次第に症状は悪化し、昭和53年9月には右足を引きずり、頭部が反り返る動きが出現した。近所の医療機関で見てもらったところ、「あなたは心身症です」と診断され、精神安定剤を処方された。この処方薬で一時的に症状は軽快したようだったが、その効果は長く続かなかった。再び症状は悪くなり、日大板橋病院に精査治療のために入院となる。私がOさんと会ったのがこの頃だった。
神経内科での診断は晩発性全身性ジストニア。この疾患に効果があるといわれている各種薬剤を試みるも著効を得られず、外来follow upとなった。昭和55年6月になり、「眼、口、頭、頸、それに手足と、体全体に自分では制御出来ないクネクネとした運動が出て困る。仕事もこんなことではできないし、頭痛、不眠、口渇、呼吸困難まで起こしている、何とかして欲しい」と訴えて来た。「それならもう一度最初から服薬の調整をしてみましょう」と、大学の関連病院に入院をして頂いて、じっくりとその効果を見ながら、どの薬剤がこのdystoniaに有効なのかを研究することになった。詳細については省くが、この臨床研究から、dopamineを介する神経伝達物質の脳内病態について若干の知見を得ることが出来たし、薬理学的思考と錐体外路系疾患治療とが自分の中で見事にリンクして、scientificな喜びを感じることが出来た。そして、何よりもOさんのdystoniaを見事に良くすることが出来たことが喜びであったし、この経験を通じて神経内科医としてのスキルアップが得られたと思う。以下がその時に書いた論文だ。
 |
(DYSTONIAに対するSULPIRIDEの効果:神経内科治療,Vol.2, No.1, P19-24, 1985.)
この論文では、Oさんのような全身性の重症なdystoniaのみならず、書痙や職業的な局所性dystoniaについても薬物治療を試みて、良い効果が得られている。
 |
Oさんの治療経過を示したのが下の図だ。26年前だから、もちろんボツリヌス治療はなかった。placeboを作って患者に分からないように投与すると症状は悪化し、実薬に戻すと症状は確実に改善した。
 |
表面筋電図を記録したのが以下の図だが、sulpiride投与後にきれいにdystonic movementが消失しているのが分かる。
 |
sulpirideというのは面白い薬剤で、D2-dopamine receptor遮断作用によりパーキンソニズムを呈し、抗ドパミン作用によりプロラクチン分泌が促進し、乳中分泌が増す。治療薬としては、低容量では「胃・十二指腸潰瘍」に適応があり、高容量では「統合失調症」に、中間量で「うつ病、うつ状態」に適応がある。その上ここに示したようにdystoniaに効果がある。製薬会社は同じ系統の薬剤であるtiaprideの開発を進めていたらしく、こちらの方でdystonia, dyskinesiaに対する効能を取ったので、sulpirideでのdystonia治療は勢いを失った。私にすれば大変残念なことなのだが、これも時の運というものだろう。
ということで、dystoniaについては神経内科医としての専門性を持ちながら、興味深く見守ってきたつもりだった。しかし、Tさん達の患っているspasmodic dysphoniaに関してはまったく蚊帳の外だった。よく調べてみると、欧米では音声言語病理学者(speech language pathologist)というスタッフがいて、その働きによってこうした異常な状態を早くから認識することになったようだ。
 |
(http://www.youtube.com/watch?v=OlZDloYcaTQ&feature=relmfu)
このYoutubeのvideoを見て頂くと、ここらへんの経験と歴史の深さが分かる。
そして、簡単な局所麻酔を皮膚の表面からしただけで、針筋電図で声帯および周囲の筋活動を探りながら、目的の筋にボトックスを注入する様子は、まさにありふれた日常診療そのものである。
 |
(http://www.youtube.com/watch?v=KiUlZV6YDYM&feature=related)
このような手技が日本でも一般的なものになって可笑しくないはずであるのに、ある限られた医療機関でしかやられていないことに驚く。欧米でも日本でも、このボトックス治療は耳鼻咽喉科の医師によってやられているようだが、神経内科医が同じように行って可笑しくない手技だ。
日本では、ボトックスは「眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸、上肢痙縮、下肢痙縮及び2歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足以外には使用しないこと」となっている。spasmodic dysphoniaに日本では使用しないことになっている理由は、添付文書にある[ミオクローヌス性ジストニー及び内転型の攣縮性発声障害の患者で、本剤による治療中に因果関係を否定できない死亡例の報告がある]という記載によっているようだ。しかし、欧米でこれだけ日常的に行われている治療法が、日本で否定される科学的な理由が示されているわけではない。今後は欧米との格差を埋める経験や技術の移転、情報開示や患者による治療法選択の自由を進めて行く必要がある。その上で、現在診療報酬上医療保険の適応になっている「眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸、上肢痙縮、下肢痙縮及び2歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足」に加えて、spasmodic dysphoniaについても、その適応を拡大して対処すべきだろう。
Tさんと同じ病気の方が、日本にも数千人単位でいるといわれている。その人達が当たり前のように、自分たちの病気がどんなもので、どのような治療が可能だと、日本中のどこの医療機関に行っても医師から詳しく話が聞けるようになって欲しい。もちろん、まだこの病気の全容が分かっているわけではない。そうした意味では、患者さん達が専門医と共にさらにこの病気の原因に迫ることが出来るように、より良い医師・患者関係がつくられることを望んでやまない。