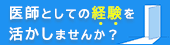分岐点での決意(上)
2009年5月15日 コンサルタントS
「終末期医療の道に進みたい…」と、K先生からのメールが届いたのは余寒なお厳しい頃だった。「整形外科医でありながら、なぜ終末期医療の道なのだろう」と、とても不思議に思ったが、早速、連絡し、面談の日程を調整した。
K先生はとても朗らかな面持ちで、見るからに全ての患者様に対して優しく接してくれそうな雰囲気をお持ちの方であった。関西の国立大を卒業され、整形外科医の道に進まれたK先生は8年間、臨床を経験された。その後、整形外科医としてのスキルアップと、更なる知識の吸収のため、アメリカのM大学に3年間、留学されたという。留学先では整形外科医として骨軟部腫瘍の基礎研究をされたが、帰国後は再び臨床の道に戻り、整形外科医として一線級のキャリアを積んでいらした。
整形外科医として忙しくも充実した日々を過ごしていたK先生だが、終末期医療の道を考え始めたのは、ご自身の家族の問題と、このまま続くであろう忙しい毎日に対応していくことが出来るのか、という不安が大きくなったからだという。
「整形外科医としての仕事は大好きです。しかし、精神的にも体力的にもこのまま続けていけるかと考えると不安で仕方がないのです。今は40歳代ですから無理も利きますが、3年前に子どもが生まれ、家族との時間を真剣に考え始めた頃から将来に対する不安が大きくなってきました」
我々サラリーマンでも同じことを考えるが、医師不足のこのご時勢、医師の労働時間は、我々サラリーマンとは比べ物にならないほど異常である。まして人命を預かる職業上、その重圧は計り知れない。
そこで急性期医療を離れ、終末期医療の道に進むことを強く望むようになっていったそうだ。
「自分自身、疲弊している事も大きな原因ですが、数年前に父親をガンで亡くしたとき、緩和ケアに対する知識が無く安らかに送ることが出来なかったことを後悔しているのです。だからこそ終末期医療の緩和ケアを学びたいのです」
私はK先生の話を聞きながら、「そこまで疲弊しておられるならば、そんな考えに至るのも仕方がない」、「いや、ここまでのキャリアを何とか生かす方法はないか」、「K先生に提案できるベストな道はないのか」、と頭の中で逡巡した。
これから緩和ケア科に入職となると、他科での臨床経験があるとはいえ、病院としてはK先生に後期研修医的な立場しか用意できないのが現実だろう。すると当然ながら現在よりも低い年収になってしまうし、研修医としての立場が40歳代の医師にとって、別の意味で疲弊してしまう恐れがあることを伝えた。
K先生はしばらく考え、「それでは今のスキルを生かした別の道は考えられますか?」と質問され、私は返答に困ってしまった。しかし、私と同い年でもあるK先生の転職を絶対に何とかしてあげたいという思いが強くこみ上げた。
そのとき、昨年末に訪問したTリハビリテーション病院が整形外科医を募集していたことをふと思い出した。
「これだ!」と思い、それまでの暗い雰囲気をかき消すかのように、私はTリハビリテーション病院について、K先生に説明し始めた。
K先生は今まで急性期病院の整形外科医として勤務されており、リハビリテーション中心の回復期病院の内容をあまりご存知でないようだった。
私は回復期医療のこれからの必要性や、術後の機能障害を最小限に抑えるためのリハビリ医療の重要性や、急性期を脱し、容態の安定した患者様のフォローアップやオぺのない医療についても話した。加えて、これまでのようなオンコール体制での拘束や、一刻を争う緊迫した状況とは離れるけれども、整形外科医としての経験が十分に活かせる職場であり、何より体力的、精神的な負担がかなり軽減される職務であることも説明した。
また、終末期医療で安らかに送ることもとても重要な仕事だが、急性期を脱しこれから回復しつつある患者様の手助けになる医療もまた重要な仕事では?と問いかけたところ、K先生からは「それならば是非検討してみたい」との返事をいただいた。
しかし、K先生はリハビリの経験がないことをただ一つの問題点として挙げ、「やはり始めは研修医的な扱いになってしまうのでしょうか」と質問された。
その点に関しては昨年末にTリハビリテーション病院を訪問した際に、「未経験でも患者様とのコミュニケーションが上手く取れる先生であれば構いません」との返答をいただいていたので、あまり心配はなかったが、再度、募集内容の確認を取ることを約束して、最初の面談を終えた。